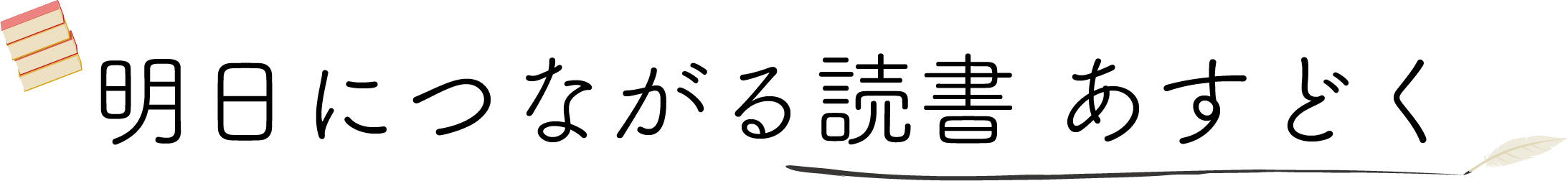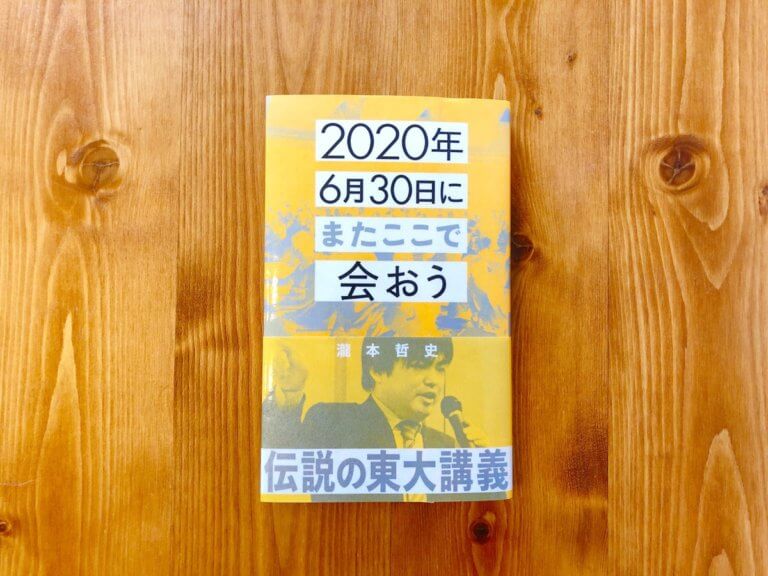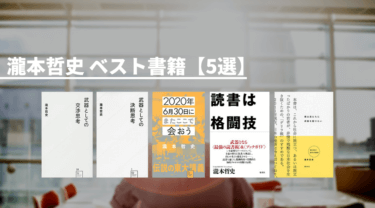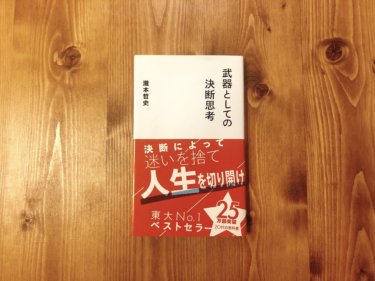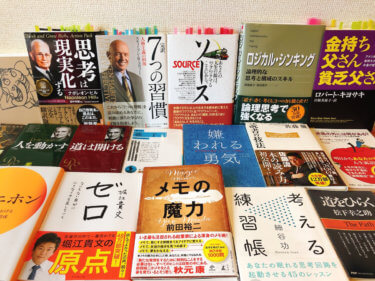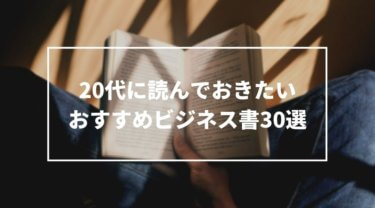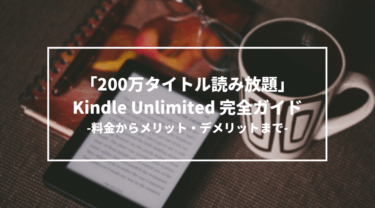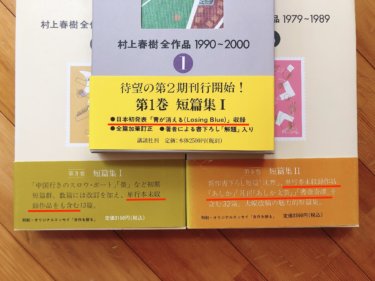ぼくは実際には瀧本哲史さんにお会いしたことはありませんが、ぼくの読書人生に大きな影響を与えた方の一人であることは間違いありません。
「若者にこそチャンスがある」「自分の頭で考えて生きていけ」というような力強く、そして一貫した言葉の数々に勇気づけられてきました。
そんな瀧本さんが去年、病のため47歳という若さでこの世を去ったことを知ったときは、驚きを隠せませんでした。ぼく個人としてもショックでしたし、日本という一国に与えた損失でもあったと言っても過言ではない気がします。
生前ではエンジェル投資家としてベンチャー企業の成長を助け、経営コンサルとしても活躍され、京都大学客員准教授として若者の教育にも貢献してきた瀧本さん。
企業論、交渉術、思考術などのテーマで書籍を出版されてきましたが、今年、2012年6月30日に東京大学で行われた講義をもとに一冊の本が出版されました。
それは『2020年6月30日にまたここで会おう』です。本書を読んだ感想は、「瀧本さんがこれまで伝えてきたメッセージのエッセンスが詰まったような本だな」というようなものでした。
「若い立場で自分はどう生きていくべきか」という悩みを抱えている人は、本書を足がかりに瀧本さんの本に興味が出るかもしれません。
「周りに振り回されず、自分で決断した人生を送りたい」と思っている人にとっても、その実現可能性を高めるようなヒントを得られる場が見つかるでしょう。
ここでは本書『2020年6月30日にまたここで会おう』から、絶対に触れておいた方がいいというような瀧本哲史の名言とも言える重要なメッセージをいくつか抜粋して紹介していきたいと思います。
▽こちらに瀧本さんの書籍要約&レビューをまとめました!ぴったりの一冊を見つけませんか?▽
ビジネスの世界では瀧本哲史さんの名前を知らない人の方が珍しいかもしれませんが、そんな瀧本さんの本質的で超実用的な知識が詰まった本を5冊に厳選して紹介していきたいと思います。 瀧本さんに関しては以下で少し詳しく述べますが、主に日本の未来[…]
なぜ考えることは大事なのか

誰かすごい人がすべてを決めてくれればうまくいく、という考えはたぶん嘘で、「みなが自分で考え自分で決めていく世界」をつくっていくのが、国家の本来の姿なんじゃないかと僕は思っています。
世界のルールや「当たり前」というのは、昔に誰か偉い人が決めて当然のようにそこにあるものとして認識されがちです。しかし、それらも誰かの決断で作られたものにすぎませんし、それが現在必ずしも正しいかどうかはわかりません。
僕たちが生きているこの社会のルールというのは、資本主義、自由主義、民主主義の3つになります。
考えることの重要性は、これらのルールを理解することで明白になります。本書の瀧本さんの解説をベースに、資本主義、自由主義、民主主義をそれぞれ超簡潔に説明するとこうなります。
資本主義とは、「誰が正しいかわからない」から、いろんな人がアイデアを出して、自己責任でやってみる。その結果上手くいったものは生き残り、ダメなものは消滅していくゲーム。
自由主義とは、みんなが好きに活動できる社会。拘束されるのは基本的にお互いが納得して取り決めた契約などがある場合のみ。
民主主義とは、契約や法律のような社会全体のルールを、市民みんなが自分たちで決める社会。
となります。そしてなぜこれが「考えること」につながるかというと、
この資本主義、自由主義、民主主義をきちんと成立させるために共通して必要なのが、じつは、さっき言った「自分で考え自分で決める」ことなんですね。
考える枠組みこそが「教養」

この「考える」ということは、口で言うほど簡単なものではないのも事実です。「誰か」や「何か」に頼りたくなる気持ちもわかる、と瀧本さんですら言います。
しかし、そんな心の弱さに負けてはいけません。
ではどうすればいいかというと、地図やコンパスも持たせず、大海原に身一つで投げ出すなんてことは、瀧本さんはしませんでした。
自分で考えるためにはやっぱり、考える枠組みが必要なんです。その枠組みが教養であり、リベラルアーツであるということです。
最近では「教養」や「リベラルアーツ」という言葉はよく聞きますし、書店に行っても、そのような言葉をテーマにした書籍が並んでいるのを見ます。
では具体的にその「教養」とはなんなのか。何を学ぶべきかというと、
僕は、「言語」がもっとも重要だと思っています。
言葉の二種類の機能

「言語」というのも、これまたかなり抽象的な言葉ですよね。勘違いしてはいけないのが、ここで言う「言語」が、英語を学べだとかプログラミング言語を学べというような話ではありません。
みなさんが普段日常的に使っている言葉、日本語、そこに秘められているすさまじい力を知って、とことん磨きあげてほしいんですよ。
そうです。日本語です。
「そんなの生まれてこのかたずっと使いこなしているよ」と思うかもしれませんが、言葉の力は無限大です。本書で瀧本さんはこの「言葉」の機能を二つに分けて解説しています。
まず一つが「ロジック」つまり論理です。「誰もが納得できる理路を言葉にすること」です。
瀧本さんの著書『武器としての決断思考』では、まさにこのロジックをテーマとしています。
人生に悩みはつきものですが、重要なのは「後悔しないために、どのように意思決定をするか」という点ではないでしょうか。 進学か就職か、企業か起業かフリーランスか、家は買うべきか賃りるべきか... などなどあらゆる場面で重要なものから[…]
また、言葉のもう一つの機能が「レトリック」、日本語では修辞と呼ばれるものです。レトリックは「言葉をいかに魅力的に伝えるか」です。
瀧本さんは、このレトリックの重要性を、無名だったバラク・オバマさんを大統領にまで押し上げたこと、明治維新という革命を世界的に見ると少ない犠牲で成し遂げられたのは言葉の力があったこと、などの例によって強調しています。
日頃当たり前に使っている言葉。日本語。この可能性をぼくたちは軽視しているのかもしれません。
今日から「言葉マニア」になってほしいと思います。
この瀧本さんの一言は、ポップでありながら、かなりの想いが込められたメッセージであると、ぼく思うのです。
行動することの重要性
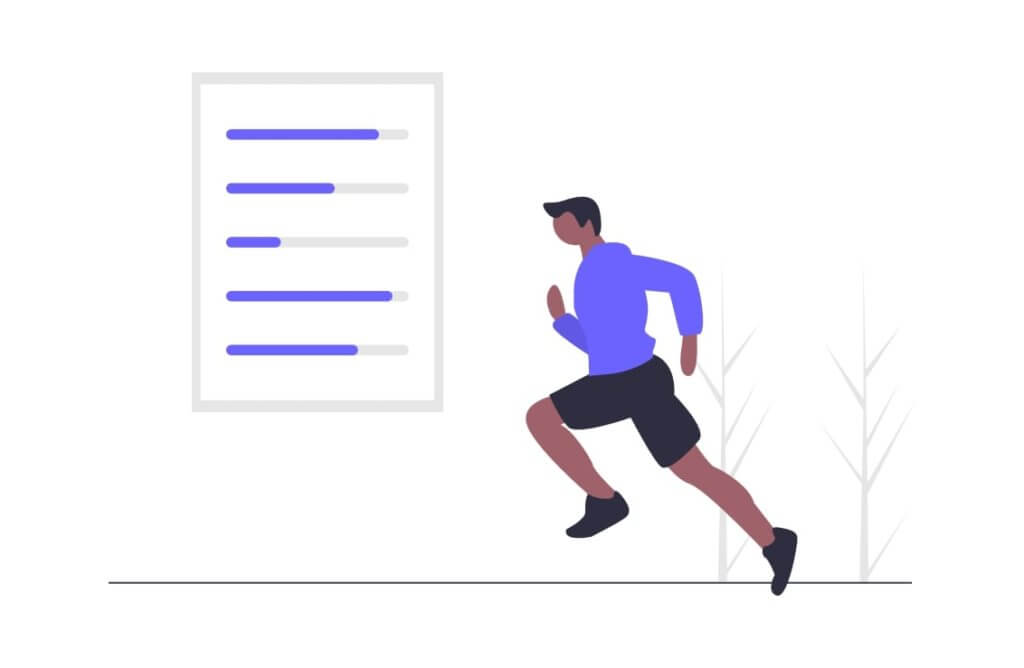
考えることの重要性、また考える力を鍛えるには言葉を鍛える必要があることは上記で述べました。その考えることと同じくらい重要なことは「行動すること」です。
本を読むだけではあんまり意味がないということです。
もちろん本を読むこと自体を否定しているわけではないと思います。
しかし本を読んで、何かしらの感想を持ち、また何事もなかったかのうように生活に戻っていく。そんな読書では意味がなくて、どれだけの人が行動にうつしているかが重要だと瀧本さんは言っています。
何か自分で、これはちょっと自分ができそうだなっていうことを見つけるとか、あるいはできそうなやつにやらせてみるとか、そういうことを地道にやっていくという方法でしか、たぶん今の世の中を大きく変えるということはできないのかなというふうに僕は思っております。
本書の話の締めとして、このようなメッセージが残されています。
いきなり大きなことにチャレンジする必要はありません。派手な成果を狙わなくてもいい。ただ、「そんなの無理に決まっている」と何も行動せず、批判ばかりしているような人たちより、自分ができることを少しずつでも行動にうつしていく人の方が断然価値があるのではないでしょうか。
言葉と行動。
この二つの武器さえ持っていれば、今後の生き方がずいぶん変わったものになっていくのではないでしょうか。少しずつでも、世の中を変えていくことすらできるのではないでしょうか。少なくともあって困るものではない!そう思わせてくれるのが、本書『2020年6月30日にまたここで会おう』でした。
『2020年6月30日にまたここで会おう』を行動にうつす
本書『2020年6月30日にまたここで会おう』に学ぶ、明日から始めたい行動内容は、
ロジック力(論理力)を磨く
です。
言葉の機能の一つであるロジック。これを意識して鍛えることからはじめましょう。もう一つの言葉の機能であるレトリック(修辞)についての訓練もできるとよいのですが、まずはロジックです。
この論理的思考力を鍛える本は、今後も紹介していきたいと思いますが、読んだことがない方はまず、瀧本さんの『武器としての決断思考』をおすすめします。
▽瀧本哲史さんのこちらの本もおすすめです!▽
ビジネスの世界では瀧本哲史さんの名前を知らない人の方が珍しいかもしれませんが、そんな瀧本さんの本質的で超実用的な知識が詰まった本を5冊に厳選して紹介していきたいと思います。 瀧本さんに関しては以下で少し詳しく述べますが、主に日本の未来[…]
それでは楽しい読書ライフを!
<<こちらも読まれています>>
「読書に馴染みがない人にもオススメの」「絶対に読むべき」必読のビジネス書をテーマに、1位から30位までのビジネス書ランキングを紹介します。今話題の起業家の著作や長く読み継がれる名作まで幅広く網羅する一方で、あまり知られていない隠れた名著もラ[…]
社会人になって間もない20代は知的好奇心が旺盛で、学びの吸収が早く、その後の30~40代以降の仕事体力の基礎を築く大事な時期です。 「若さ」という武器で多くの新しいことにチャレンジし、まだまだ失敗が許容される時期でもあります。そんな人[…]
アメリカの名門大学トップ10の学生が課題図書として読んでいる本をランキング形式で紹介します。 世界を見渡しても、大学のランキングはアメリカがトップを独占しています。ハーバード大学1位、マサチューセッツ工科大学2位、スタンフォード大学3[…]
【関連記事】
あなたがAmazonユーザーや読書家なら、200万冊もの本を読み放題のサービスKindle Unlimitedについて気になっていませんでしたか? 「Kindle Unlimitedはお得なのか」「元は取れるのか」「使い勝手はどうなの[…]
近年、新しい読書の形としてオーディオブックという耳で聞くスタイルが浸透してきています。中でも有名なのがAmazonが提供するAudible (オーディブル) というサービスです。運動や運転などをしながら「ながら読書」ができるのが魅力です。 […]
村上春樹作品の長編小説しか読んだことはない方はもちろん、短編集もほとんど読んでいる方でも、見逃している作品があるのではないでしょうか。 村上春樹の公式に公開されている短編小説は現時点で約100を数えますが、そのほとんどは短編集という形[…]