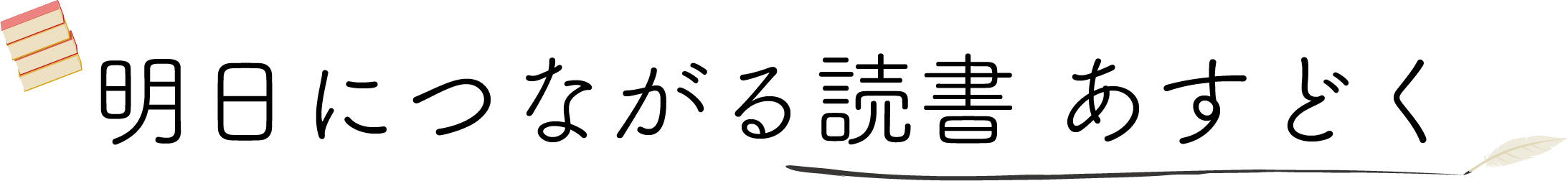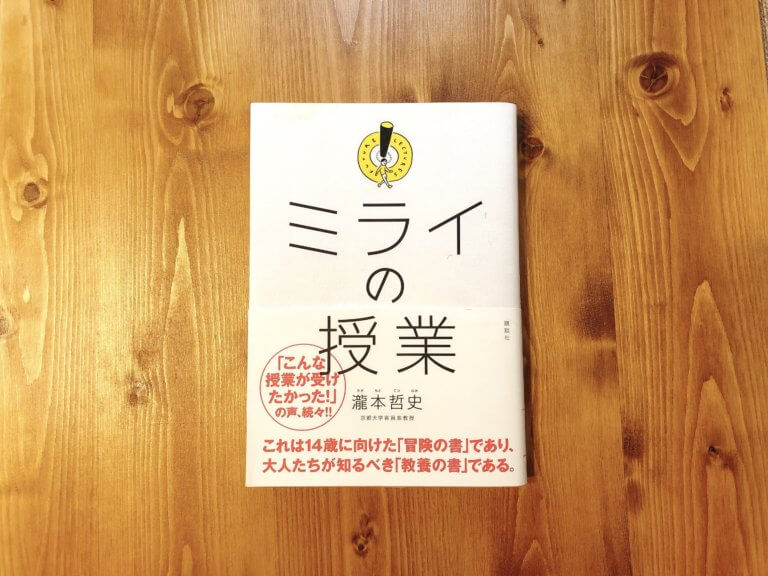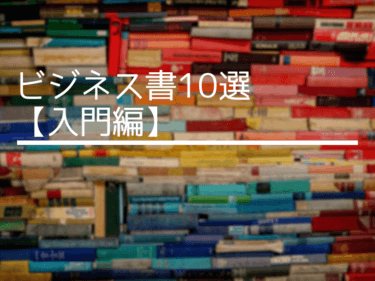昭和から平成、平成から令和、と元号が変わると同時に、いやそれ以上の速さで時代は変化しています。主にテクノロジーの進化が加速し、人間の代わりにAIやロボットが仕事を請け負う時代が来るであろうこの社会で、どのように生きていけば幸せになれるのでしょうか。
今回は『ミライの授業』というビジネス書を紹介したいと思います(もちろんここで紹介する以上、ビジネス書とは言っても誰もにとって役立つ内容です)。
本書の著者・瀧本哲史さんは経営コンサルタントやエンジェル投資家という肩書きを持ちつつ、京都大学で客員准教授として教鞭をとっていました。残念なことに2019年に多くの人に惜しまれつつ、他界しました。日本の宝のような人だったと言えるでしょう。
そんな瀧本さんは多数著書を残していて、その一冊が本書『ミライの授業』です。
この本では、京都大学で日本の未来を担う大学生に向けて行なっている、あたらしい時代を生き抜くための講義の内容が、14歳でも理解できるように話されています。
これは14歳に向けた「冒険の書」であり、大人たちが知るべき「教養の書」である。
上記は本書の帯に書かれている内容ですが、まさに子供であろうと大人であろうと誰が読んでも、今後生きるために必要な知識が学べる内容となっています。
今後未来を生きていく上で重要な法則が五つ紹介されていますが、ここではぼくが特に重要だと思って厳選した三点を軸に「今後を生き抜くヒント」を紹介していきます。
『ミライの授業』はどんな内容?
本書では、著者の瀧本さんが京都大学にて大学生に教えていた「あたらしい時代を生き抜くための講義」をどの年代の読者にもわかるように説明してくれている、いわば瀧本哲史さんの入門書です。「変化する未来を見守るのではなく、その未来をつくる側にまわろう」と主張し、過去に世界を変えた偉人たちに学びながら、これからどのようにものを考えていけばいいかを学んでいきます。
学校などで学ぶことの重要性、親世代とは環境が異なるこの時代での思い込み、などに気付かされます。本書では主に「違和感」「地図」「ルール」「影の主役」「逆風」という五つのキーワードで、講義形式に展開されます。今後を生きるための教養を学ぶ入門書とも言えるでしょう。
疑うこと
日常のなかのちょっとした違和感に気づき、一見当たり前なことに疑問を持つことが重要だと、瀧本さんは言います。
変革者たちは、自分のなかに芽生えた「小さな違和感」を掘り下げ、常識を疑い、ウソを見破ることから、冒険をスタートさせてきました。
例えば「万有引力の法則」で有名なアイザック・ニュートン。彼は「りんごは木から落ちるのに、なぜ月は落ちてこないのだろう」と疑問に思ったことは有名です。
若いうちは、大人の常識に染まり切っていないから本質的な疑問を持ちやすい、というのはたしかにそうかもしれません。
ですが、大人になっても疑問を持つことはできます。
目や耳に入っているのに、それを気にもせず、通り過ごしているだけなのです。
「そんなの昔からそうだよ」「決まってることなんだから」と自動的に頭の中で処理してしまい、疑問になる前にそんなもやもやは消えていってしまいます。
しかしふと違和感や疑問を持ったときは、立ち止まってみましょう。書き留めてみましょう。
そしてそれを考え抜くことが重要です。では、どう考えればよいか。
疑問を持ったらまず「本質を考える」ことです。目的を考えることと言い換えることもできるかもしれません。
例えば、移動手段や運送手段が馬車だった時代に、人はもっと速く移動したいと考えました。そこでたいていの人は、もっと速い場所を作る方法を考えました。
しかし、今や有名なアメリカの車メーカー・フォード・モーターの創業者であるヘンリー・フォードは違いました。
簡単に言うと、馬車ではなく車を生み出したのです。
「そもそも速い移動手段って馬車でなくてはならないのだろうか?」という疑問を持ち、「目的は速く移動すること」という本質に立ち返り、馬車という枠から外れた新しいアイデアを生み出したのです。
一見なんの不自由もないこの時代では、このように疑問を持ち、課題を見つける人が重宝されます。目の前に課題があり、いかにその課題をクリアするかということを考えていればよかった世代とは根本的に異なるのです。
仮説を持つ
冒険に出るときに地図が必要なのと同様に、ぼくたちの人生においても「地図」が必要だと言います。
そして、ここで「地図」を指すものは、仮説です。
自分が抱いた違和感や疑問をもとに、自分なりの仮説を持つことが重要です。
「〜をこうすればもっと世の中良くなるのではないか?」というような仮説です。
ただしこの仮説に正確さはいりません。
細かいところは間違っていても、おおよその全体像がつかめること。そして「こっちに進めば、目的地にたどり着くんだ!」という大まかない行き先がわかること。
この変化が多い時代で、計画通りに物事が運ぶことはまずないと言っていいでしょう。なので冒険に出る前にいくら細かく地図を書いてもあまり意味がないのです。
実際に身をもって経験し、学んだことから、その仮説を微調整していけばよいのです。
しかし、大まかな方向性を間違ってはいけません。
例えば、数ある鉱山の中から金を探し出すときに、何も考えずいち早く穴を掘り始めるのが正解でしょうか。どれだけがんばって穴を掘り続けても、そこに金はないかもしれません。
それよりも、どこに金が埋まっているのかをいろいろな情報を照らし合わせて見極めた上で、可能性が高く、早く辿り着けそうな場所を選ぶことが重要です。
この仮説を立てる場所について、「空白地帯」を選ぶことがポイントだと瀧本さんは言います。
たくさんのライバルがひしめくなかで手を挙げても、「その他大勢」になってしまうだけ。自分よりも優秀な人たちがいる可能性も高いでしょう。
例えば、みんなが金がたくさん埋まっている場所で穴を掘るとします。そこでは競争が起きます。金が埋まっている可能性が高いからといって、同じ場所を大人数で狙いに行くと、得られる金が減ってしまうばかりか、いずれ体力も消耗し、金も尽きてしまうかもしれません。
一方、誰も狙いに行かないような場所で、「ここにはダイヤモンドが眠っているかもしれない」という仮説を立てれば、競争もせずに、より大きな成果が手に入る可能性があります。
競争が多い分野をビジネス業界では「レッドオーシャン」と呼び(争って血が流れるイメージ)、穴場な「空白地帯」を「ブルーオーシャン」と呼びます。聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
最近「ブルーオーシャン」のような言葉をよく聞くのは、「空白地帯」を狙ったほうが有利な時代だからという背景があるからなんですね。
信じた道を進む
疑問を持ち、仮説を持って、さあ自分の道を進もうとする場合、最終的に最も大事なのが、「自分の道を信じる」ということです。
みなさんが世界を変えようとするとき、自分の夢をかなえようとするとき、周囲の大人たちが応援してくれると思ったら大間違いです。大人たちが応援するのは、自分の地位を脅かさない若者だけ。つまり「世界を変えない若者」だけです。
瀧本さんが言うように、今の既得権者(良い思いをしている人)は、その立場を覆されることを恐れています。すでに地位を確立した「大人」が現状を維持しようとするので、イノベーションや革命は起きにくいのは当然かもしれません。
しかし、若い世代や世の中をより良くしようという信念を持つ人にとっては、そのような「大人」は逆風でしかありません。
ライドシェアや自動車の自動配車を実現したUberは、そのような逆風を日本で受けているサービスの一つです。簡単に言うと、Uberはより安くより簡単にタクシーに乗れるサービスを提供してくれます。
しかし、それで売り上げが落ちるかもしれないのが、タクシー業界です。彼らはUberの日本進出を妨げている要因の一つです(個人の見解です)。
このように誰かの反対で、自分が信じた道でも挫折してしまいそうになるかもしれません。
しかし、あなたのことを真剣に思って反対する人はどれほどいるでしょう。
反対をする人というのは、たいてい
- あなたが羨ましいから
- 自分が損をするから
- 自分が知らないものだから
という場合がほとんどではないでしょうか。
しかし反対されたときこそがチャンスだと勇気づけてくれる言葉がこちらです。
賛成する人がほとんどいないとき、周囲のみんなが激しく反対するとき、それでも自分が「これは大切な真実なんだ!」と思えるとき。みなさんは世界を変える第一歩を踏み出しています。
何をするにもあなたにとって遅すぎるということもなければ、早すぎるということもありません。
新しいチャレンジは何歳からはじめてもいいのです!
明日からはじめよう!
『ミライの授業』に学ぶ、明日からはじめたい行動内容は、
日常の疑問を書き留める
です。
「なんでポストは赤いんだろう?」「なぜ銀行では印鑑が必要なんだろう?」など、なんでもいいと思います。何気なく思ったことは、驚くべきスピードで忘れてしまいます。瞬時にメモを取り、「なんで?」「なんのため?」とその物事の根本を考えてみましょう。
あなただけが見つける「より良いアイデア」が生まれるかもしれません!
他にも学べること
□世の中のルールについて
□自分が活躍できる場・助けてもらうべき場について
□おすすめ書籍
etc.
何歳になっても未来をつくることはできる。目覚めることはできる。そう気づかされる一冊です。「自分の頭で考えもせず、漫然と生きていることに気づいてしまった。」そう思わされるビジネス書の紹介でした。
14歳にもわかる語り口なので、非常に読みやすいのが本書の特徴です。
「休みに本でも読むか」と意気込んでいる方。 「むずかしい本は苦手だな」という意識を持っている方。 「読書はあまりしないけど、なんか本読みたいな」と意欲に湧いている方。 「自分の成長のために読書をしたいけど、どんな本を読んだ[…]