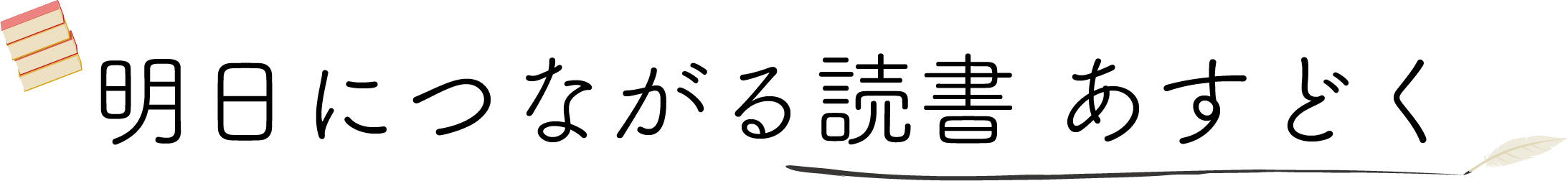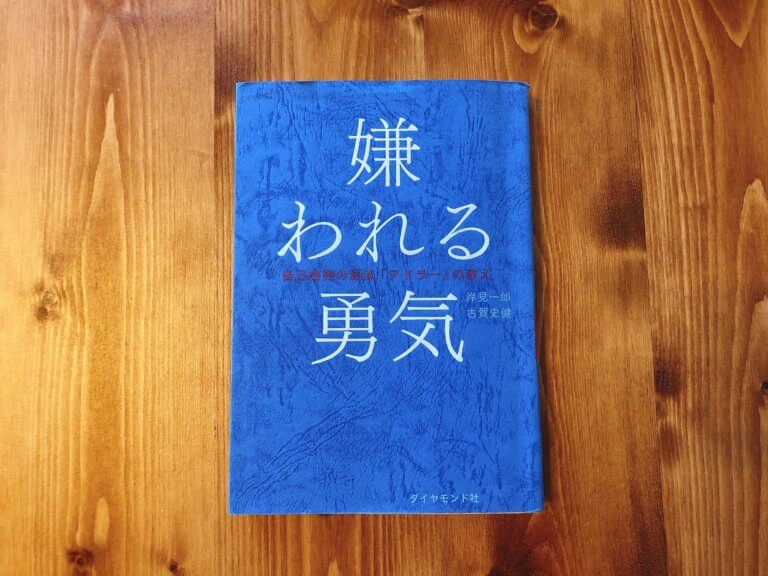今回紹介する本は、『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』です。『嫌われる勇気』は書店やテレビなどで一度は見たこと・聞いたことがある人も多いかと思います。
『嫌われる勇気』はアドラー心理学についての本で、アドラー心理学というのは、フロイト、ユングと並び、心理学の三代巨頭と称されるアルフレッド・アドラーが創設した心理学です。オーストリア出身の精神科医であるアドラーが提唱した、まったく新しい心理学は、現在僕たちが生きるこの時代にこそ助けとなってくれるような考え方だと考えられています。
現在の悩みについて、漠然としたものではなく、「具体的な処方箋」のような答えをくれるのがこのアドラー心理学なのです。特に、
「幸せってなんだかよくわからない」
「過去のトラウマを引きずってしまっている」
「人からよく思われたいから人の目ばかり気にしてしまう」
などという悩みを持っている人にこそ読んでほしい一冊が、この『嫌われる勇気』です。
『嫌われる勇気』はどんな内容?
幼い頃から自信が持てず、学歴や容姿についても強い劣等感を持っている青年。そんな青年が、とある哲人と対話して進んでいく物語形式となっています。哲人はアドラー心理学に基づいて、カウンセリングのように青年の悩みに対してアドバイスを送ります。さまざまな悩みを持つ青年にとって、はじめは哲人の主張はすべて絵空事にしか感じられませんでした。この青年に自分を投影してしまう読者は多いでしょう。
過去のトラウマに対する考え方や、人間関係、ひいては全ての悩みを解決するヒントとなるような言葉をたくさん聞けることでしょう。「どうすれば人は幸せに生きることができるか」という問いに、シンプルかつ具体的な答えを提示する、それがアドラー心理学です。この青年と同じように、アドラー心理学の新しい考え方は衝撃が大きいと感じる人もいると思います。実際に自分もカウンセリングを受けている気持ちで読み進めてみると得るものは大きいはずです。
「過去」は変えられる
家庭、学校、会社、その他のコミュニティの場で体験した過去に悩んでいる人にとって、「過去は絶対に変えられない」「だから今の自分はかわいそうな状況だ」「未来にも希望が持てない」そう思うのも仕方のないことだったかもしれません。しかしアドラー心理学的には違います。「過去」は変えられるのです。
もちろん、タイムスリップをして過去をやり直そう、的なSF的展開ではありません。正確には「過去の体験で感じたことを変える」ということです。例えば、本書『嫌われる勇気』では、過去に親から虐待を受けるなどの原因で、家にこもりっきりになっている人を例にあげます。
「不安だから、外に出られない」のではありません。順番は逆で、「外に出たくないから、不安という感情をつくり出している」と考えるのです。
普通は家庭の暴力、学校でのいじめ、その他何らかの原因があって、引きこもりになってしまったと考えるのが一般的ですよね。これをトラウマと言ったりしますが、要は原因があるから今がある、という原因論です。
一方、アドラー心理学では、トラウマを明確に否定します。
過去の経験に「どのような意味を与えるか」によって、自らの生を決定している。
つまり、その家庭の暴力、学校でのいじめなどについて、自分がどう考えるか、どう感じるかが重要ということです。たしかにすでに起こってしまったそのような出来事をなかったことにはできません。しかし、その体験をどう捉らえるかは本人次第なのだといいます。「惨めな体験をしてしまった。つらい。もう誰にも会いたくないし、外にも出たくない」と考える人もいます。しかし「たしかに辛い出来事だった。誰にもこの辛さはわからないかもしれない。でも自分の人生こんなところで終われない。こんなどん底を経験したんだから、これから先はこれより良い未来が待っているに違いない」と思えるか。
この両者では今後の人生は全く違ったものになるのは明白です。「アドラー心理学は、勇気の心理学です。」
人間の悩みの根本
人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである
人間の悩みの根本、それは対人関係だと、アドラー心理学では考えます。一見、自分自身の悩みのようでも、それは誰か他人に関連しているのです。
例えば、「身長が低いことがコンプレックスなんだよな」という悩みは、対人関係と別の問題であるように考えがちです。しかし、その「身長が低い」というのは、他の誰かと比べて低いということに他なりません。「競争」や「勝ち負け」から生まれた劣等感なのです。
身長という客観的な数字や見た目は変えることができませんが、その身長をどう考えるかは主観的な問題であって、自分で変えることができます。「これくらい身長があればな」という理想は、他者との比較で生まれるべきではありません。人は人だし、自分は自分なのです。
「大切なのはなにが与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである」
僕はこのアドラーの言葉が大好きです。他人と比べて、無い物ねだりをし、嫉妬し、悩み、ストレスを感じるより、自分が持っているものを尊重し、感謝したいものです。
承認欲求はどうでもいい
ちょっと言葉が乱暴すぎるかもしれませんし、承認欲求というのは誰しもが持っている欲求の一つです。しかし近年よく聞くようになったこの承認欲求に振り回されている人は多いかもしれません。SNSで良い感じの写真や文章を投稿して、「いいね」をもらいたい。頑張った分誰かに認められたい。
多くの人がそのような考えのもと、行動するのは、賞罰教育の結果だと言います。適切な行動をとったら、ほめてもらえる。不適切な行動をとったら、罰せられる。僕たちの多くは、幼少期からそう学んできました。しかし、本書のこの言葉を今一度じっくり考えてみましょう。
われわれは「他者の期待を満たすために生きているのではない」
また、こうも言います。
他者の視線を気にして、他者の顔色を窺いながら生きること。他者の望みをかなえるように生きること。たしかに道しるべにはなるかもしれませんが、これは非常に不自由な生き方です。要するに誰からも嫌われたくないのでしょう。
グサグサと痛いほどに身にしみた人も多いのではないでしょうか(僕自身もあっけにとられてしばらくぼーっとしてしまいました…)。相手のためだと思って自分がやっていることは、果たして本当に相手のためなのでしょうか?自分がよく思われたいだけでは?嫌われたくないだけでは?
そう問い直すと多くの自分の言動が、承認欲求のため、誰かに嫌われたくないだけ、であることに気づきます。
たしかに他人に言われたこと「親のために」とか、上司に言われたことを「怒られないために」とか考えて生きることはそれほど難しいものではありません。むしろ楽なものです。でも結局、全員の思いを汲んで、全員から好かれようなんてできません。どれも中途半端になって全員から信用を失うことだってあるでしょう。
一番大きなポイントは、自分の行動によって相手がどう思うかは相手次第ということです。
その選択について他者がどのような評価を下すのか。これは他者の課題であって、あなたにはどうにもできない話です。
それならもう幸せになるために変えられる部分は自分でしかありません。自分がどうしたいのか、どう感じたいのか。そこで本書のタイトル『嫌われる勇気』につながるのです。
「他者から嫌われろ」と言っているのではありません!
「嫌われることを恐れるな」ということです。
明日からはじめよう!
『嫌われる勇気』から得るべき明日からはじめられる行動内容は、
自分がどう感じているかを考える
ことです。何か嫌なこともしくは嬉しいことがあったときに自分が何を感じているか、一度立ち止まって考えてみましょう。それは相手のためでしょうか?それとも自分のためでしょうか?
自分の人生を生きるためにも、その出来事に縛られることなく、他人に嫌われることを恐れず、自分に正直になりましょう。
他にも学べること
□イライラしたときの対処法
□「人生のタスク」
□信用と信頼の違い
□仕事の本質
etc.
メンタル系のビジネス書が最近増えてきていますが、多くの本の根底にあるのがこのアドラー心理学だったりします。アドバイスが具体的でありながら、応用範囲が広い本質的なものばかりなので、自分の中に基礎を気づくためにも、『嫌われる勇気』は一度は読んでおきたい本です。対話方式で進んでいくので、読書が少し苦手だなという人でも読めてしまうと思います!