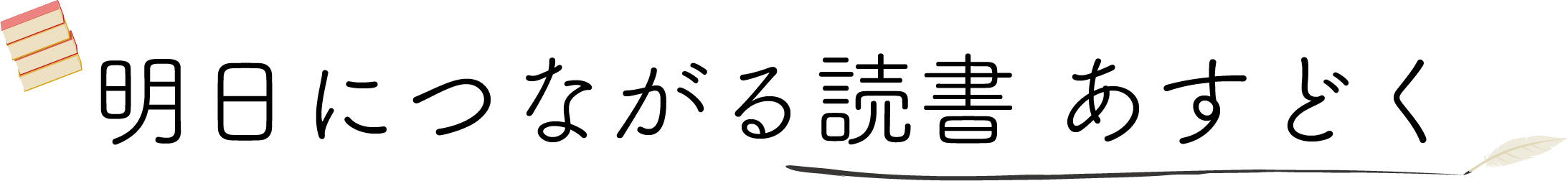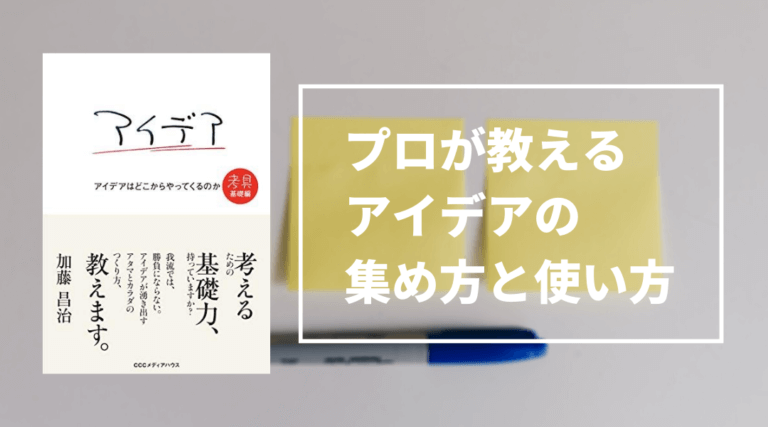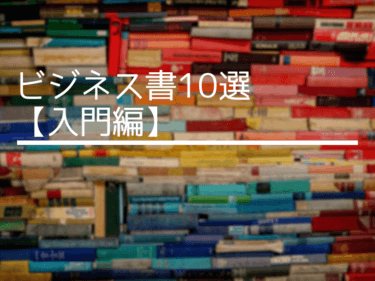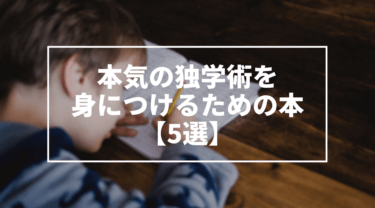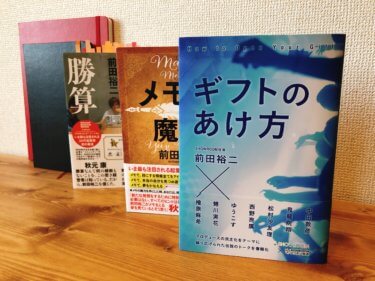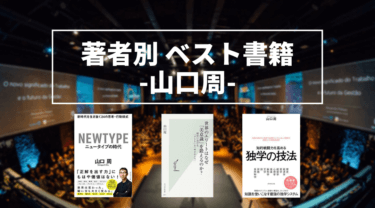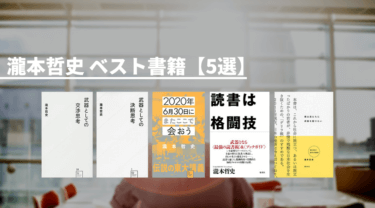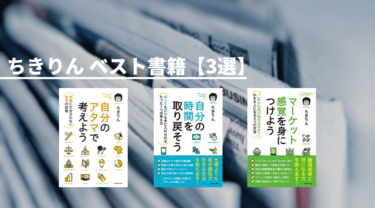考えるための武器『考具』に引き続き、ここでは加藤昌治さんの『アイデアはどこからやってくるのか 考具 基礎編』を紹介していきます。アイデアはどのように集めればよいのか、さらにそのアイデアをどのように使っていいくべきかというプロの知識を学びましょう。
本書は、より具体的「もっと細かく具体的にプロがアイデアを生み出す過程が知りたいな」と思う人には特におすすめです。
アイデアの集め方
アイデアと聞くと、クリエイティブな人しか生み出せないと考える人もいるでしょう。しかしアイデア自体はそんなに大そうに考えるべきものではありません。アイデアは企画の素でしかない、と加藤さんは述べます。
結果的に起業や問題解決のためのきっかけになるかもしれませんが、アイデアの段階では妄想で思いつきでテキトーでOKなのです。そして企画のための単なる選択肢と考えると、量をたくさん出す必要があります。アイデア出しは量がものをいうのでとにかく良いものばかり考えようとせずに、自分ではくだらないと思うものでもどんどん出していくことが重要です。
この段階ではわがままであることで楽しく、広くアイデアを出すことができます。わがままとは私利私欲とは違い、素直になるということです。さまざまな制約や実現可能性は、いったん無視します。
これがアイデアをつくる上での基本姿勢です。
ではアイデアとはなんなのか?
『アイデアのつくり方』という名著で知られるジェームス W.ヤングの有名な言葉ですが、
「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせでしかない」
つまり全く新しいゼロからイチを生み出すようなものではなく、すでに知られているもの同士の組み合わせこそがアイデアなのです。
そしてそのなかで加藤さんが特に重要視しているのが、いかに既存の要素を集め、いかにその蓄積された要素をコントロールしていくかです。
まずアイデアを集めるための源泉を分解すると以下の4つに分けられます。
1. 直接体験
自分自身で見て、聞いて、触ったものです。これがやはりキーとなるでしょう。生活そのものにヒントもありますし、旅などの非日常の中にも刺激的な要素を集めるきっかけはたくさん眠っているでしょう。
2. 間接体験
時間は有限な中で時間と空間を飛び越えることができるのがこの間接体験です。他の人のレビューや小説、体験記などあらゆる情報がネットや本からアクセスできるの上に低コストなのが魅力です。ただどの程度信じていいかの判断は重要です。
3. 知識
新聞などのマスメディアなどから得られる単なる情報を指します。
4. まだ知らないこと
これが世の中の大半を占めますが、自分では認識していない情報や知識を指します。
アイデアの使い方
では集めたアイデアのもととなる要素をどのように活用していけばよいのでしょう。加藤さんは自分の記憶を「24時間循環風呂」にすべきだと述べます。
集めた要素・記憶をそのままにしておいたのではすぐに忘れしまうし、せっかく新しい要素が頭に入ってきても、記憶の中の要素と結びつかないのでは意味がありません。つねにそれらの要素を流動的にしておく必要があります。
そのためには、「できるだけ頻度高く、それぞれの体験・知識を脳裏に思い浮かべる」ことと「それぞれの体験・知識に複数のアプローチでたどり着ける」という意識が重要となります。
ではこれらを実現させるにはどうすればよいのでしょうか。
キーワードは「たぐる」です。
「たぐる」とは、アイデアにするために既存の要素を活性化させる手段が「たぐる」です。
「たぐる」を辞書で引いてみると
1. 両手で代わる代わる引いて手元に引き寄せる。
2. 物事をそれからそれへと引き出す。一つ一つもとへたどる。
とあります。
本書では、イメージがしやすいようにケーススタディとして実話を紹介してくれています。
I. 「たぐる」の発端はとあるコミック。洋服の仕立て職人の話。ここで無性に「仕立て」というコンセプトに惹かれる。
II. そのコミックを通じてスーツに「ナポリ仕立て」なる流派があるのを知った。
III. 仕立て職人たちはどんな裁ちばさみを使っているんだろう?と検索
IV. ネットをふらふらしていたら、某県にすごい爪切りがあることを知る。
V. 自身が割りと爪を伸ばしがち。恥ずかしい思い出甦り…一人赤面。
VI. そして疑問生じる。「人はいったいそのくらいの頻度で爪を切っているんだろう?」
VII. この時点で最も気になっていること。失礼のない範囲で、会う人ごとに聞きまくっている状況。
始まりからは半年くらい経っているらしいですが、ここに一連の「たぐる」プロセスがあります。直接体験、間接体験、各種メディアでの知識をたぐり寄せていくことで、自分の中にひとつの「既存の要素」ができあがっていく感じです。
ここでもわかった通り、いつでも自分の外と中をたぐれる(アクセスできる)ことが大事なのです。
この「たぐる」を4つに分解した小技を紹介していきます。
1. ぶつかる
知らなかったものと出会い、それを一度許容すること。「へえ」をスルーせず、なにか感じたものがあるはずなのでメモするなど引っかけておきます。日常の中にこそ探すべきですし、意識的に「今日はぶつかるか」とあまり興味のない本を読んだりすることでも機会は増えるでしょう。
ケーススタディ該当番号: I, II, IV
2. 思い出す
とあるきっかけから過去の記憶が表面化することなどがあるように、自分の内側にたぐることを指します。なつかしい曲を聞いてそのときの思い出がばーっと流れ出てくるとかありますよね。
ケーススタディ該当番号: V
3. 押さえる
外部にむかって情報を求めていく下調べのようなものです。ネットや本を駆使してそのテーマや問題に対して軽く全体像を把握します。ここでのポイントはあくまで軽く。正確な調査というよりはアイデアへのヒント探しが主な目的です。
ケーススタディ該当番号: III
4. 掘る
さらにディープにそのテーマを掘り下げていきます。幅広い領域でアイデアを出せるのは強みですが、ある分野について深く知っていて突出したアイデアが出せるのも強みです。加藤さんは早い段階で1つか2つの分野を掘ることをオススメしています。
必ずしも高いコストをかけて専門誌の購読や専門家へのヒアリングなどをする必要はなくて、とりあえず「なんちゃって専門家」を目指す。まずは会社の中で一番詳しい人になってしまいましょう。例えば本を20冊読んでもいいでしょう。
ケーススタディ該当番号: VII
いかがでしたでしょうか。得体のしれない、天才しか生み出せないと思っていた「アイデア」を身近に感じることができたでしょうか。
まずは、「たぐる」の「ぶつかる」から始めてみましょう!意識的に自分の知らないモノ・コトで出会うようにするのです。街に出るでも本を読むでもいいでしょう!
具体例やアイデアの増やし方などについても書かれていますが、その説明については本書に譲ることにします。
それでは楽しい読書ライフを!
▽他にもオススメしたい本がたくさんあります!▽
【テーマ別ベスト書籍】
「休みに本でも読むか」と意気込んでいる方。 「むずかしい本は苦手だな」という意識を持っている方。 「読書はあまりしないけど、なんか本読みたいな」と意欲に湧いている方。 「自分の成長のために読書をしたいけど、どんな本を読んだ[…]
「自分の頭で考える」 これからの時代を生きていく上で、最も重要な能力がこれではないでしょうか。 テクノロジーの発展が著しいこの時代で、これまで人間がやっていた仕事の大部分を、AI/人工知能やロボットが代替することが可能になると言[…]
最強の独学法を学ぼう 独学がテーマの本5選 社会人になってまでなぜ勉強を続ける必要があるのでしょうか? その答えは「世の中が変わるからだ」と主張するのが経済学者の野口悠紀雄さんです。 まさにAIやその他テクノロジーなどの進[…]
▽その他おすすめ著者別書籍を厳選しました!▽
学生時代に起業した会社を上場させ、その後約2年半の服役生活を送り、今では誰よりも自由なライフスタイルを実現させているホリエモンこと堀江貴文さん。そんな堀江貴文さんの生き方や思考は、自らが配信するメルマガや数多く出版されている書籍などに記され[…]
今や最も知られる起業家であり、作家・TVコメンテーター・オンラインサロン主催者などとしての顔も持つ前田裕二さんについて、掘り下げていきましょう。 現在、前田裕二さんの著作は三冊出版されています。自身の半生記やビジネスについてまとめた『[…]
今回は山口周さんの優先して読むべき本を4冊に厳選して紹介していきます。山口さんをご存知の方は、おそらくこの中の1冊は読んだことがあるかもしれません。 山口周さんは大手広告代理店や外資系コンサルなどを渡り歩いた異色のキャリアを持つ方です[…]
ビジネスの世界では瀧本哲史さんの名前を知らない人の方が珍しいかもしれませんが、そんな瀧本さんの本質的で超実用的な知識が詰まった本を5冊に厳選して紹介していきたいと思います。 瀧本さんに関しては以下で少し詳しく述べますが、主に日本の未来[…]
ここでは社会派ブロガーとして知られるちきりんさんの本で、特におすすめしたい3冊の著作を紹介したいと思います。 「社会の問題に対して鋭い考察を持ち、客観的なデータやわかりやすい図などを使い説明してくれる」 ぼくはちきりんさんに対し[…]